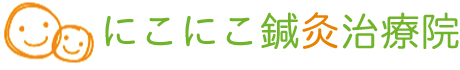■この記事の筆者は当院の院長が書きました。院長プロフィールはこちらへ。公開日:2025年1月4日 更新日:2025年10月29日
痛風の鍼灸施術について

■痛風による症状の改善は期待できます!
痛風とは風が当たった軽度の刺激でも痛みが出るというところから名付けられています。
痛風は現代医学では薬の服用するのと食事療法を併用することがベーシックな治療になりますが、実は鍼灸でも改善が期待できるのです。
では鍼灸施術によって患者様が得られるベネフィット(利益)ですが、それは・・・
①発作時痛みの早期改善が期待できる。
痛風発作を起こした後の24時間でピークを迎え、それから徐々に痛みが落ち着いてきます。軽度の場合で2・3日位かかります。その間はつらい痛みとの戦いになりますが、鍼灸を行うことで痛む期間がより短くそして痛みの程度も我慢できる程度まで改善が期待できます。風が当たるでも痛いと感じる痛風が少しでも早く楽になるのは患者さんの利益につながりますね。
②鍼灸は痛みを取るだけでなく、発作を起こさないよう予防が期待できます。
発作を経験した方なら良く分かると思いますが、二度と発作を経験するのは嫌だと思うはずです。さらに今度、発作いつ来るだろうか心配になるはずです。
そういった方は鍼灸を定期的に続けることで体調を管理することができ、その結果として痛風の予防も期待できます。
こんな感じで簡単にまとめましたが、もう少し詳しく知りたい方はここから下をご覧くださいね。
①発作時痛みの早期改善が期待できる。
痛風発作を起こした後の24時間でピークを迎え、それから徐々に痛みが落ち着いてきます。軽度の場合で2・3日位かかります。その間はつらい痛みとの戦いになりますが、鍼灸を行うことで痛む期間がより短くそして痛みの程度も我慢できる程度まで改善が期待できます。風が当たるでも痛いと感じる痛風が少しでも早く楽になるのは患者さんの利益につながりますね。
②鍼灸は痛みを取るだけでなく、発作を起こさないよう予防が期待できます。
発作を経験した方なら良く分かると思いますが、二度と発作を経験するのは嫌だと思うはずです。さらに今度、発作いつ来るだろうか心配になるはずです。
そういった方は鍼灸を定期的に続けることで体調を管理することができ、その結果として痛風の予防も期待できます。
こんな感じで簡単にまとめましたが、もう少し詳しく知りたい方はここから下をご覧くださいね。

■現代医学では・・・
●痛風とは・・・
・原因は尿酸値が高くなることによって、関節内に尿酸塩結晶ができてしまいます。これを白血球が処理する時に急性の関節炎(痛風発作)を起こしてしまうからです。
・尿酸値が高いまま放置しておくと尿酸結石が腎臓に生じて、腎臓に影響を及ぼすと腎機能を悪化させ、腎不全を起こします。
・なぜ尿酸値が高くなる理由ですが、①腎臓からの尿酸を排泄する力が低下。②暴飲暴食・肥満・激しい運動③ストレス
などが原因と考えられます。
●主な症状・・・・
・暴飲暴食をした次の日、急に足の親指の付け根が赤く腫れて痛くなることがあります。
足の親指だけでなく、足の関節(足首)・足の甲・アキレス腱の付け根・膝の関節(ひざ)・手の関節(手首)にも激痛になることがあります。
・耳たぶに痛風結節・尿路結石ができる場合もあります。
・生活習慣病(肥満・高血圧等)を併発している場合もあります。
などが原因と考えられます。
●主な症状・・・・
・暴飲暴食をした次の日、急に足の親指の付け根が赤く腫れて痛くなることがあります。
足の親指だけでなく、足の関節(足首)・足の甲・アキレス腱の付け根・膝の関節(ひざ)・手の関節(手首)にも激痛になることがあります。
・耳たぶに痛風結節・尿路結石ができる場合もあります。
・生活習慣病(肥満・高血圧等)を併発している場合もあります。

●治療について
・痛風は「薬物療法」による痛風発作時の鎮痛と食生活習慣による「予防」の2つからなります。
まず薬物療法として
①解熱鎮痛剤を投与します。
・ロキソニンを服用することで痛みの緩和を図ります。
②局所麻酔入りのステロイド注射をします。
・関節内に注入することで痛みの緩和を図ります。
➂コルヒチンを投与します。
・この薬剤で痛風発作の鎮静化を図ります。
次に予防として「野菜中心の食生活に変えて尿酸が体内にできないようにする」か「内服薬で血中の尿酸値を下げる」の2つがあります。
・痛風は「薬物療法」による痛風発作時の鎮痛と食生活習慣による「予防」の2つからなります。
まず薬物療法として
①解熱鎮痛剤を投与します。
・ロキソニンを服用することで痛みの緩和を図ります。
②局所麻酔入りのステロイド注射をします。
・関節内に注入することで痛みの緩和を図ります。
➂コルヒチンを投与します。
・この薬剤で痛風発作の鎮静化を図ります。
次に予防として「野菜中心の食生活に変えて尿酸が体内にできないようにする」か「内服薬で血中の尿酸値を下げる」の2つがあります。
| 【 参考ページ 】 ・痛風とは|日本整形外科学会 |

■鍼灸では・・・
鍼灸では痛風という病名はありません。東洋医学では「痺証(ひしょう)」に当てはまります。
*学術的に一般の痺証とは風邪(ふうじゃ)・湿邪(しつじゃ)・寒邪(かんじゃ)の3つの邪気(じゃき)が混じり合った物が、関節に滞ることによって痛みが生じることを言います。もう少し細かく言うと3つの邪気の他に瘀血(身体に不要な血液)・痰(身体に不要な水分)が組み合わさって症状が出る場合があります。
●原因
ストレス・飲食不摂生・体調不調を押して無理をした等により、親指に流れる経脈(脾経と肝経:「ひけい」と「かんけい」と言う)に「風邪」・「湿邪」・「寒邪」の3つの邪気が滞り、気血(きけつ)の流れが悪くなったことにより風が当たっても痛い(痛風)状態になったと考えます。病態がこじれてしまうと「寒邪から熱邪)に変化し患部に影響を及ぼします。さらにこじれてしまうと内臓にも影響を及ぼします。そのような場合は邪気だけでなく、瘀血(おけつ)や痰(たん)と言った身体に不要な血液や水分が悪さを起こします。
●施術方法
①3つの邪気が混じった中でどの邪気が中心で症状が発生させているかを判断します。
例えば風邪(ふうじゃ)が中心であれば「痛みがあっちこっちに動く」という特徴があり、湿邪(しつじゃ)が中心であれば「ジトッとした邪気の為に重怠く痛む場所も一定」の特徴があり、寒邪(かんじゃ)が中心であれば「冷えて痛みが激しく場所は同じ」という特徴があり、熱邪(ねつじゃ)が中心であれば「現代医学で言う炎症の状態」という特徴があり、患者様の状態からどの邪気が中心で症状を発生させているのか判断します。
②どの邪気が中心で症状を発生しているかが分かったら、それに応じて施術します。
例えば風邪が中心であれば「血を増やば自ずと風邪がなくなる」という原則を元に肝血を補います。
湿邪が中心であれば「気を増やせば水の代謝が改善される」という原則で脾胃を補います。
寒邪が中心であれば「温めれば自然と寒邪はなくなる」という原則でお灸で熱を補います。
熱邪が中心であれば「熱を散らす」という原則で鍼もしくは灸(特殊なお灸方法)で患部の熱を散らす。
ストレス・飲食不摂生・体調不調を押して無理をした等により、親指に流れる経脈(脾経と肝経:「ひけい」と「かんけい」と言う)に「風邪」・「湿邪」・「寒邪」の3つの邪気が滞り、気血(きけつ)の流れが悪くなったことにより風が当たっても痛い(痛風)状態になったと考えます。病態がこじれてしまうと「寒邪から熱邪)に変化し患部に影響を及ぼします。さらにこじれてしまうと内臓にも影響を及ぼします。そのような場合は邪気だけでなく、瘀血(おけつ)や痰(たん)と言った身体に不要な血液や水分が悪さを起こします。
●施術方法
①3つの邪気が混じった中でどの邪気が中心で症状が発生させているかを判断します。
例えば風邪(ふうじゃ)が中心であれば「痛みがあっちこっちに動く」という特徴があり、湿邪(しつじゃ)が中心であれば「ジトッとした邪気の為に重怠く痛む場所も一定」の特徴があり、寒邪(かんじゃ)が中心であれば「冷えて痛みが激しく場所は同じ」という特徴があり、熱邪(ねつじゃ)が中心であれば「現代医学で言う炎症の状態」という特徴があり、患者様の状態からどの邪気が中心で症状を発生させているのか判断します。
②どの邪気が中心で症状を発生しているかが分かったら、それに応じて施術します。
例えば風邪が中心であれば「血を増やば自ずと風邪がなくなる」という原則を元に肝血を補います。
湿邪が中心であれば「気を増やせば水の代謝が改善される」という原則で脾胃を補います。
寒邪が中心であれば「温めれば自然と寒邪はなくなる」という原則でお灸で熱を補います。
熱邪が中心であれば「熱を散らす」という原則で鍼もしくは灸(特殊なお灸方法)で患部の熱を散らす。

■セルフケアについて・・・
・当院でおススメするセルフケアは「お灸によるツボのケア」と「食事療法」になります。
①お灸によるツボのケア。
院長が良いと考えるツボを3つ挙げてみます。
-
〇大都穴
 大都(だいと)穴は脾経のツボで足の親指にあります。ここは痛風で痛いと感じる部位の近くにあるツボになります。
大都(だいと)穴は脾経のツボで足の親指にあります。ここは痛風で痛いと感じる部位の近くにあるツボになります。
ここに灸をすることで脾胃の働きが改善されて、身体に不要な物(水分)の排出を促し、痛風にならないように予防が期待できます。 -
〇大敦穴
 大敦(だいとん)穴は肝経のツボで風邪を追い払うツボになります。
大敦(だいとん)穴は肝経のツボで風邪を追い払うツボになります。
ここに灸をすることで体内に入った身体に不要な邪気(風邪)を外部に排出を促すことで痛風の予防にもつながりますよ。 -
血海穴
 血海(けっかいと読み、位置は黒い点)穴は脾経のツボで血の不足を補ったり、瘀血(不要な血液)を取り除く重要なツボになります。痛風から内臓に影響を及ぼす時には瘀血がからんでくるので瘀血を取り除くにも大切なツボになります。
血海(けっかいと読み、位置は黒い点)穴は脾経のツボで血の不足を補ったり、瘀血(不要な血液)を取り除く重要なツボになります。痛風から内臓に影響を及ぼす時には瘀血がからんでくるので瘀血を取り除くにも大切なツボになります。

②東洋医学の観点からみる食事療法について
・東洋医学では医食同源と言って食事も重視しています。
今回は痛風ですので、俗にいうプリン体をいかにして減らすかが現代科学では考えられていますが、東洋医学の場合、以下のように考えます。
・東洋医学では医食同源と言って食事も重視しています。
今回は痛風ですので、俗にいうプリン体をいかにして減らすかが現代科学では考えられていますが、東洋医学の場合、以下のように考えます。
・寒邪が中心で症状が出ている場合ですと体を温める物(しょうが・にら・魚全般・火を使った料理)を多めに食べて頂くといいです。反対に身体を冷やすような食べ物はNGです。例えば氷菓子等。
・湿邪が中心で症状が出ている場合ですと胃腸の働きを改善が期待できる「肉類」を多めに取って頂くといいです。反対に甘い物や生ものは控えて下さい。食べ過ぎると脾胃に負担がかかりかえって不要な水分が溜まりやすくなるからです。
・熱邪が中心で症状が出ている場合ですと、身体を冷やす食べ物(野菜全般・果物の一部)を多めに食べて頂くと良いです。反対に身体を温めるような食べ物はNGです。例えば唐辛子を使った料理等。
・湿邪が中心で症状が出ている場合ですと胃腸の働きを改善が期待できる「肉類」を多めに取って頂くといいです。反対に甘い物や生ものは控えて下さい。食べ過ぎると脾胃に負担がかかりかえって不要な水分が溜まりやすくなるからです。
・熱邪が中心で症状が出ている場合ですと、身体を冷やす食べ物(野菜全般・果物の一部)を多めに食べて頂くと良いです。反対に身体を温めるような食べ物はNGです。例えば唐辛子を使った料理等。
| 【 詳細ページ 】 ・東洋医学の考え方 【 参考文献 】 ・薬膳食典食物性味表|日本中医食養学会 |
まとめ
・現代医学では痛風は食事療法(プリン体をいかに取らないか)が重要だと説いています。食事療法でも難しいもしくは食事療法ができない場合は薬でコントロールが必要になりますね。
・鍼灸では痛風の治療と痛風の予防と両方とも可能です。痛風発作時は全身調整と患部の施術で症状を改善を目指し、症状が安定してきたらどんな条件で発作が起きたか分析して、施術をすれば予防効果も期待できます。例えば発作時に痛みが非常に激しい状態だった場合、寒邪が中心で起きている状態ですので、寒邪に影響を及ぼしやすい「腎」の働きを改善する施術を行うことになります。
・痛風はプリン体だけでなくストレス等で尿酸値が高くなる場合もあるので、注意深く観察する必要があります。
・鍼灸では痛風の治療と痛風の予防と両方とも可能です。痛風発作時は全身調整と患部の施術で症状を改善を目指し、症状が安定してきたらどんな条件で発作が起きたか分析して、施術をすれば予防効果も期待できます。例えば発作時に痛みが非常に激しい状態だった場合、寒邪が中心で起きている状態ですので、寒邪に影響を及ぼしやすい「腎」の働きを改善する施術を行うことになります。
・痛風はプリン体だけでなくストレス等で尿酸値が高くなる場合もあるので、注意深く観察する必要があります。